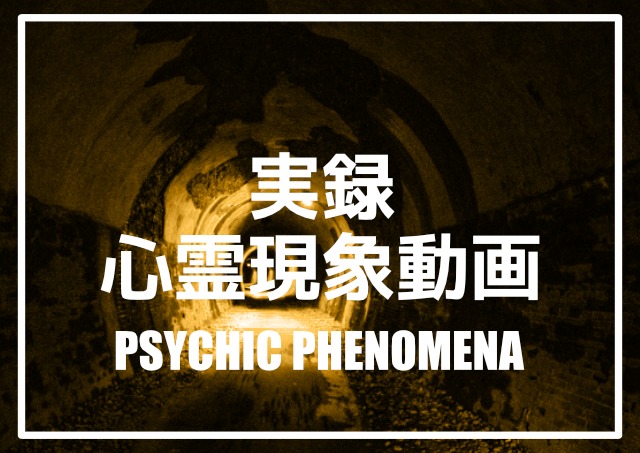住所
茨城県石岡市総社2丁目8-1
詳細情報
| 参拝時間 | 自由 |
|---|---|
| 社務所/授与所 | 9:00~17:00 |
| 電話番号 | settings_phone0299-22-2233 |
| ホームページ | http://sosyagu.jp/open_in_new |
| 主祭神 | 伊邪那岐命、須佐之男命、邇邇藝命、大国主命、大宮比賣命、布瑠大神 |
| 創建時期 | 平安期 |
常陸國總社宮のご由緒
約1300年前の7世紀、現在の茨城県は常陸国と呼ばれていました。広大で海山の幸に恵まれたこの国は全六十余国のうち最上の「大国」とされ、常世の国とも称される憧れの聖地でした。常陸国の中心地である国府があった場所が旧茨城郡、現在の石岡市です。茨城の県名はここに由来します。国府の長官である国司が執務した国衙跡の遺跡は近年の大規模発掘に伴い国指定史跡に登録されました。国衙の南側にかつて倭武天皇(ヤマトタケルノミコト)が腰掛けたと伝わる「神石」があります。日本百名山の一つ「筑波山」、日本第二の湖「霞ヶ浦」の悠々たる美景を同時に望めるこの場所に創建された「総社」が常陸国総社宮です。総社とはそれぞれの律令国に鎮まる八百万の神々を国衙近くの一ヶ所に合祀した神社であり、全国で55社が確認されています。国司たちは総社を拝することで自らが治める国の数多の神々に祈りを捧げたのです。徳川光圀が『大日本史』編纂のために参照したと伝わる社宝「総社文書」は連綿と続く当宮の歴史を今に伝えています。長大な歴史の波に翻弄され祭祀を中断せざるを得なかった総社もある中で、当宮は創建以来絶えることなく「国府の神祭り」を続けて参りました。その現在の形が最大の祭典である9月の例大祭です。地域を挙げて祝われるため「石岡のおまつり」とも呼ばれ、全国から数十万人もの参拝者が訪れます。境内最古の建造物である本殿は平成28年に大規模修復を完遂し、人々の崇敬を益々集めています。
お祓い(神社・お寺)マップ