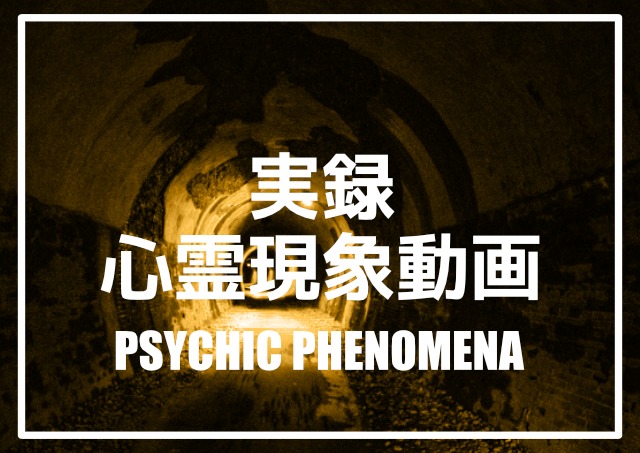住所
埼玉県児玉郡神川町二ノ宮750
詳細情報
| 参拝時間 | |
|---|---|
| 社務所/授与所 | 9:00~16:00 |
| 電話番号 | settings_phone0495-77-4537 |
| ホームページ | https://www.kanasana.jp/open_in_new |
| 主祭神 | 天照大神、素盞嗚尊 |
| 創建時期 | 景行天皇41年 |
金鑚神社のご由緒
社伝によれば、延暦20年(801年)に坂上田村麻呂が東北への遠征前に当社に戦勝祈願に参詣したという。国史の初見は貞観4年(862年)で、正六位上の神階にある「金佐奈神」が官社に列したといい、神階は同年に従五位下に昇った。延長5年(927年)成立の『延喜式』神名帳では、武蔵国児玉郡に「金佐奈神社 名神大」と記載され、名神大社に列している。『神道集』(南北朝時代)では当社を「五宮金鑽大明神」として「武蔵六所大明神(武州六大明神)」の一社に挙げるほか、本地仏を弥勒菩薩とする。また『風土記稿』によると、永禄12年(1569年)銘の鰐口にはやはり五宮と刻銘があるという。以上の史料から当社は武蔵国において五宮に列したと考えられており、武蔵国総社の大國魂神社でも五宮として当社の分霊が祀られている。一方で江戸時代の『武乾記』(安永元年(1772年))では当社は二宮と記され、地名や神社公称も二宮としているが、当社を二宮とする中世史料はなく明らかでない。神流川扇状地には九郷用水が開削され、その要所には当社の分社が祀られているが、これらの所在地は武蔵七党の1つ・児玉党の勢力範囲と一致するといわれ、同党からの当社崇敬の様子が見える。中世には同じく武蔵七党の1つである丹党の安保氏(阿保氏)から崇敬を受け、天文3年(1534年)には阿保全隆から多宝塔(重要文化財)が寄進された。また、中世から近世の社務は別当寺の大光普照寺(金鑚寺)が担ったとされるほか、戦国時代には鉢形城主・北条氏邦や御嶽城主・長井政実から保護されたという。江戸時代には、江戸幕府から朱印30石が寄進された。明治に入り、明治6年(1873年)に近代社格制度において郷社兼県社に列し、明治18年(1885年)に官幣中社に昇格した。戦後は神社本庁の別表神社に列している。
お祓い(神社・お寺)マップ