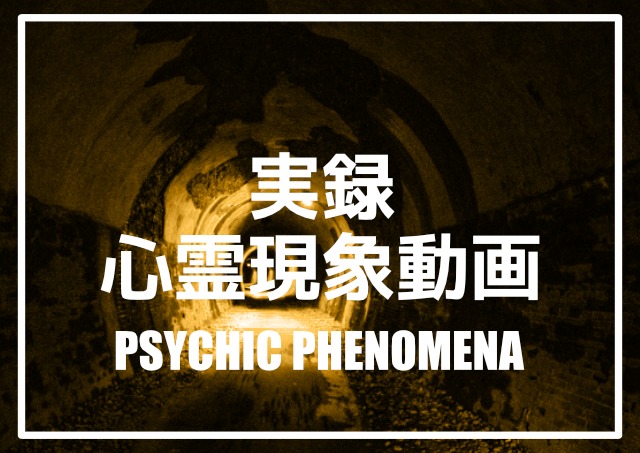住所
茨城県ひたちなか市磯崎町4607-2
詳細情報
| 参拝時間 | 自由 |
|---|---|
| 社務所/授与所 | 8:00~16:00 |
| 電話番号 | settings_phone029-265-8220 |
| ホームページ | https://sakatura.org/open_in_new |
| 主祭神 | 少彦名命 |
| 創建時期 | 856年 |
酒列磯前神社のご由緒
平安時代に編纂された歴史書である「文徳天皇実録」によれば斉衡三年(856年)12月29日に常陸国鹿島郡大洗の海岸に御祭神大名持命・少彦名命が御降臨になり、塩焼きの一人に神がかりして、「我は大奈母知、少比古奈命なり。昔此の国を造り訖へて、去りて東海に往きけり。今民を済わんが為、亦帰り来たれり」(現代意訳:私は大名持、少彦名命である。日本の国を造り終えてから東の海に去ったが、いま再び民衆を救うために帰ってきた。)と託宣され、当社「酒列磯前神社」が現在のひたちなか市磯崎町に創建され、また同時期に現在の東茨城郡大洗町には「大洗磯前神社」が創建されました。少彦名命が酒列磯前神社の主祭神に、大名持命は大洗磯前神社の主祭神としてお祀りされるに至りました。御創建の由緒からもわかるように酒列磯前神社と大洗磯前神社は二社で一つの兄弟神社となっております。御創建の翌年の天安元年8月には官社に列せられ、更に10月には「酒列磯前薬師菩薩明神」の神号を賜りました。延喜の制では名神大社に、明治18年4月には国幣中社に大洗磯前神社と共に列されました。また、昭和38年に奈良の平城宮跡の発掘調査が行われたとき、多量の木簡が出土した中に「常陸国那珂郡酒烈埼所生若海菜」と記された墨書文字が発見されました。これは今から約1300年前の昔、酒列磯前神社に奉納したこの地方のわかめを天平文化の栄えた奈良の平城宮まで頒納されていたのであり、また遠いその昔より、酒列磯前神社の御神威が顕著であり、著名なお社として全国的な尊崇を集めていたことを物語っています。
お祓い(神社・お寺)マップ