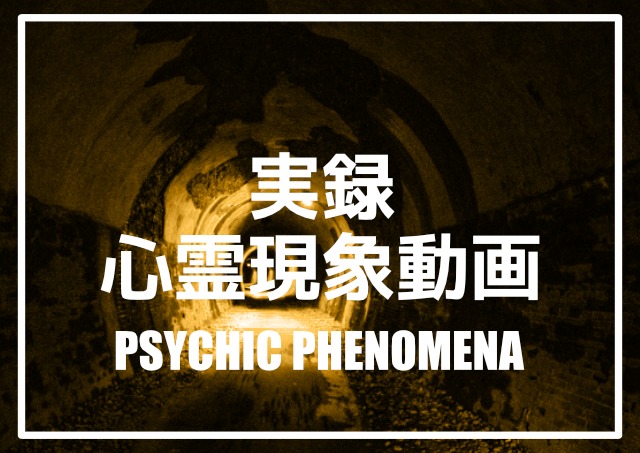住所
静岡県富士市浅間本町5-1
詳細情報
| 参拝時間 | 自由 |
|---|---|
| 社務所/授与所 | |
| 電話番号 | settings_phone0545-52-1270 |
| ホームページ | |
| 主祭神 | 大山祇命 |
| 創建時期 | 孝昭天皇2年 |
富知六所浅間神社のご由緒
伝承では孝昭天皇2年6月10日、富士山山腹に創建と伝えられる。その後噴火のため延暦4年(785年)に現在の地に遷座したとされる。崇神天皇により四道将軍として派遣された建沼河別命は当社を厚く崇敬し、勅幣を奉った。周辺に市が立ち「三日市浅間」と呼ばれるようになったという。また明和4年(1767年)に記された由緒書によると、平城天皇の大同元年(806年)に五社(当社を含む)を建立したとある。元は「六所宮」や「六所浅間宮」と呼ばれ、明治5年(1872年)に郷社に列せられると富知六所淺間神社へと改称した。中世は六所宮と呼ばれることが多く、また近世の史料である文久2年(1862年)の図では同神社を指して「冨士六所浅間宮 吉原宿ヨリ凡八丁」とある。当社は富士下方五社の1つであり、五社別当を務める東泉院(現在は廃寺)が直轄する神社であった。五社の中でも惣社とされ、永禄13年(1560年)の「富士山大縁起」で「惣社」と記される、五社の中でも筆頭にあたる神社であった。しかしその影響勢力は時代により偏移があり、駿河侵攻後に武田氏が同地を支配すると、武田信玄は元亀元年(1570年)に別当職を東泉院に代え久能寺に与えている。これは久能寺による「武運運長久之祈念」に対する恩賞として与えられたものであった。しかし武田氏滅亡から小田原征伐を経て徳川家康の関東移封を迎えると、駿河国は豊臣秀吉の影響下に入る。その際東泉院は天正18年(1590年)に別当領190石を安堵され、この190石は六所宮を含む下方五社の神領であることから、六所宮は再び東泉院の勢力下に戻っていたとされる。しかし慶長5年(1600年)の朱印状では190石が安堵されているのは東泉院ではなく久能寺の院家の1つである智勝坊であり、再び久能寺の勢力下に収まっている。またこの智勝坊は東泉院より東泉院領および富士下方別当職を譲り受けることになり、それ以後六所宮は久能寺の勢力下であった。『延喜式』神名帳中の駿河国富士郡の式内社として「富知神社」とあり、当社はその論社とされる。
お祓い(神社・お寺)マップ